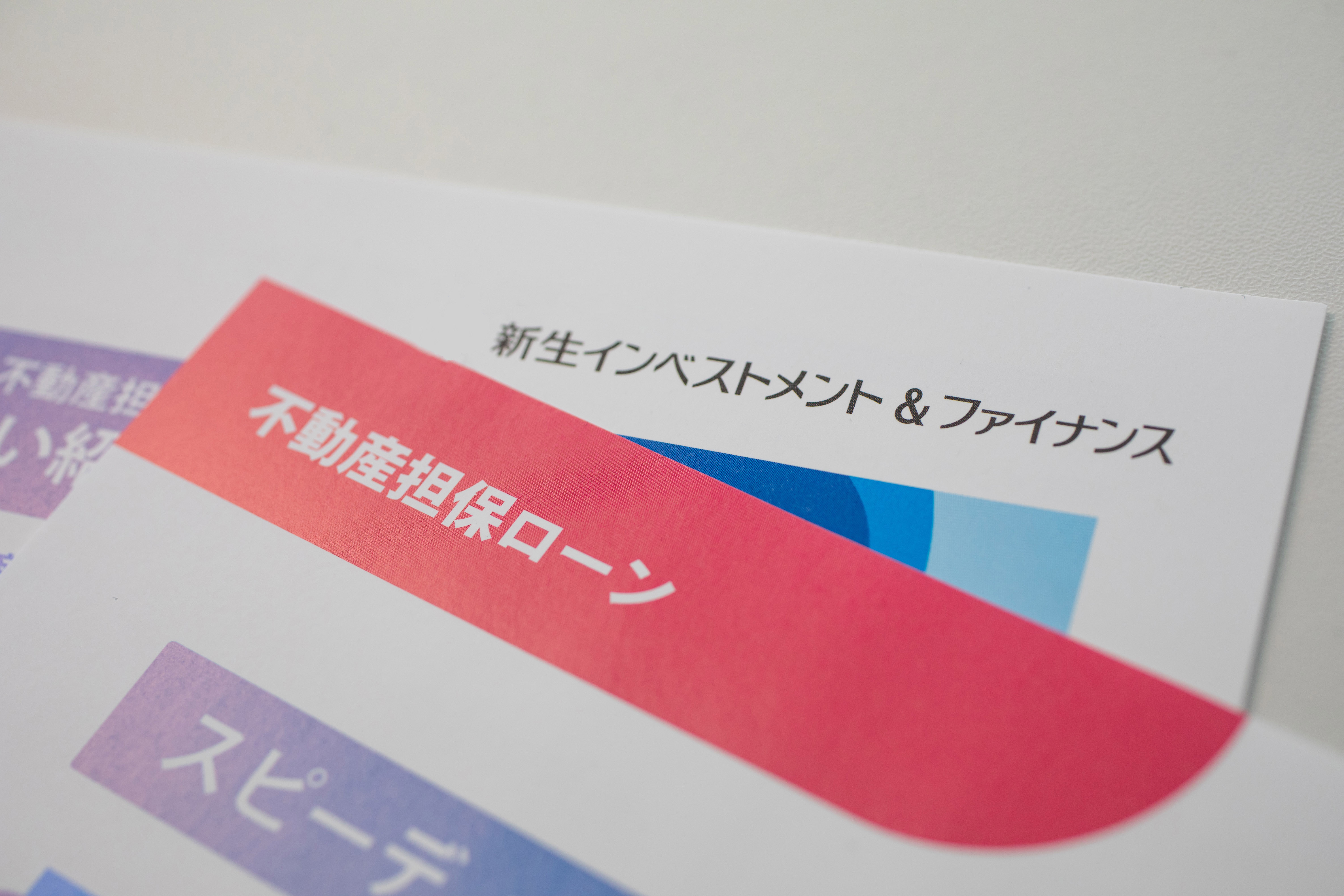新生インベストメント&ファイナンスの
不動産担保ローン
資金使途自由、最長35年までのご融資可能!
*本記事の内容は、一般的な情報を基に作成したものであり、特定の金融機関等を指したものではありません。詳細については、各金融機関等にお問い合わせください。
不動産担保ローンとは?メリット・デメリットや活用例・利用の流れを解説
不動産担保ローンは、銀行やノンバンクなどの金融機関から資金を借入れる手段の一つで、その名のとおり不動産を担保とするのが特徴です。担保がない無担保ローン商品と比較すると、借入金額は大きめ、借入金利は低め、借入期間が長いなどのメリットがあります。
一方で、無理に多額の借入れをしてしまうと、返済負担が重くなり事業のキャッシュフローを圧迫する、不動産売却による返済を余儀なくされる、などのリスクもあります。安心して不動産担保ローンを利用するためには、しっかりと仕組みを理解し、事前にきちんと返済計画を立てる必要があります。
そこで今回は、不動産担保ローンの仕組みやメリットとデメリットを改めてご説明するとともに、よくある活用例をご紹介したいと思います。どんな場面で利用されているのか、参考にしていただければ幸いです。

■この記事の監修者
山本 豊
新生インベストメント&ファイナンス株式会社 代表取締役社長
新卒でオリックス株式会社へ入社。ノン・リコースローンや不動産証券化など、ストラクチャード・ファイナンス業務に携わる。
その後、株式会社新生銀行(現株式会社SBI新生銀行)へ入社し、不動産ファンドを通じたエクイティ投資を経験。
新生インベストメント&ファイナンス株式会社で営業部門のマネジメントを経て、代表取締役社長に就任。
保有資格:日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)/不動産証券化協会認定マスター/貸金業務取扱主任者
不動産担保ローンとは
不動産担保ローンとは、融資を受ける人が所有する不動産を担保として提供し、金融機関からお金を借入れるローンです。一般的に、借入れた資金の使途は制限されておらず、自由に利用することができます。
融資限度額は、申込者本人の返済能力や担保として提供する不動産の価値によって変わります。一般的に、不動産の担保評価額(公示価格や相続税評価額などをベースにして計算する)の6割~8割程度が、融資限度額として設定されます。
担保不動産の価値次第では、数千万円から1億円を超える高額な借入れが可能です。高額な借入れを必要としている場合、不動産担保ローンは有用な資金調達の手段といえるでしょう。
ただし、返済が滞った場合は担保として提供した不動産を失うリスクがあります。事前に返済シミュレーションをおこない、計画的に返済できるか調べることが大切です。
不動産担保ローンを利用するメリット
まずは不動産担保ローンの主なメリットを4点ご紹介します。融資限度額・借入金利・借入期間・資金使途の自由度、の面で優位性を持つことをご理解いただければと思います。
融資限度額を高く設定しやすい
不動産担保ローンは、無担保のカードローンやキャッシングなどと比較すると融資限度額を高く設定しやすいメリットがあります。不動産担保ローンは、担保を差し入れてお金を借りる「有担保ローン(有担保融資)」の一種です。
数百万から億を超える資産価値を持つ不動産が担保として差し入れられるのが特徴です。そのため、担保不要の「無担保ローン(無担保融資)」と比較すると、貸し手となる金融機関にとっては、貸したお金を確実に回収できる可能性が高いローンとなり、融資限度額が比較的高い傾向にあります。
無担保ローン商品の代表格であるカードローンやビジネスローンでの借入金額の上限は1,000万円前後が多いようで、場合によっては大規模な事業資金調達ニーズに対応できません。
しかし、不動産担保ローンでは不動産の担保評価額次第では億単位の借入れも可能です。
不動産担保ローンの金額は、貸し手となる金融機関が担保となる不動産の担保評価額を鑑みて決定しますが、担保評価額がそのままローン金額となるわけではありません。不動産の担保評価額は災害や事件・事故などによって変動する可能性があるため、ローン金額は担保評価額に「担保掛目(あるいは掛目)」と呼ばれる値を乗じて算出されるのが一般的です。具体的な「担保掛目(あるいは掛目)」は金融機関によって異なりますが、60~80%程度が相場です。
つまり、担保不動産の評価額が5,000万円だった場合、不動産担保ローンを利用して3,000万円~4,000万円程度の借入れができる計算になります。
金融機関によっては、連帯保証人を不要とする不動産担保ローンを取り扱っています。借入金額が大きくなると返済負担も増すため、しっかりとした返済プランを立てたうえで申し込みましょう。
また、不動産担保ローンで押さえておくべきポイントとして、貸金業法に基づく仕組みである「総量規制」があります。総量規制により、貸金業者(「ノンバンク」とよばれることもあります)は、個人の方へは年収の3分の1を超える貸し付けはできません。
「総量規制」には除外や例外の規定もあり、すべての不動産担保ローン商品が規制を受けるわけではありません。規制の対象となるのは、個人の方がご自宅など生計のために不可欠な不動産を担保として借入れを行う場合です。総量規制に該当する借入れをおこなう場合、希望どおりの借入れができない可能性があります。
なお、ご自宅以外の不動産(賃貸アパートや駐車場など)が担保であれば、総量規制からは「除外」となります。
総量規制や不動産担保ローンと総量規制の関係については、こちらの記事で解説しています。不動産担保ローンの利用を検討している方は、参考にしてみてください。
担保があるからこそ金利が低めとなり、毎月の返済負担を抑えられる
不動産担保ローンでは不動産という物的担保があるため、貸し手となる金融機関からすると貸したお金を回収できないリスクを抑えていると考えられます。そのため、金利もカードローンやキャッシングなどの無担保ローンに比べると低い傾向にあるのです。
金融機関によって金利水準が異なるため一概にはいえませんが、金利の目安は無担保ローンが年率4%~15%程度、不動産担保ローンは年率2%~10%程度のようです。
借り手からすると、金利が低いほど返済負担が軽減されることになります。
返済期間を長めに設定できる
長期間のローンが組めるのも、不動産担保ローンの特長です。長期にわたり返済することで月々の返済金額を抑えられるのが借り手にとってのメリットです。
不動産担保ローンの場合、担保である不動産は、金融機関が担保評価額を算定するにあたって、今後数年にわたって資産価値を有すると評価しているため、貸し手となる金融機関は長期間の返済を見込んだローン商品を提供できるのです。一定の築年数が経過した建物が担保となる場合、法定の耐用年数までの残り期間を上限として返済期間が設定されるのが一般的です。金融機関により異なりますが、不動産担保ローンは最長35年の商品もあるのに対し、無担保ローンの場合は長くても10年程度とされています。
月々の返済負担を抑えながら長期で利用できるのは大きな魅力です。一方で、返済期間中は利息の負担が続き、長期間となるほど返済総額は増えることになりますので注意が必要です。
資金使途の自由度が高い
不動産担保ローン商品の多くは、資金使途に制限を設けていないようです。 自動車ローン、教育ローンなど、使い道が定められているローン商品もありますが、不動産担保ローンはそういった縛りがない場合が多く、さまざまな資金ニーズに対応できる商品といえます。住宅ローンの借換えや教育資金のみならず、事業資金などにも使用できます。ライフステージのいろいろな場面で使いやすいのがポイントです。
ただ例外もあり、主に銀行の不動産担保ローンの場合、個人向けと法人向けで資金使途の自由度が異なることもあるようです。詳細はご検討中の金融機関にお問い合わせされるのが良いでしょう。
不動産担保ローンを利用するデメリット
不動産担保ローンにおいては、借り手としてはデメリットに感じられることもあるようです。ご利用を検討される際には、次のような点も考慮されたほうが良いでしょう。
返済が滞ると担保の不動産を失うリスクがある
お金を借りたからには、返済の義務を果たさないと担保として提供した不動産を失ってしまいます。
不動産担保ローンでは、債権者(貸し手である金融機関)が担保となる不動産に「根抵当権」や「抵当権」などの担保権を設定します。万が一、債務者(不動産担保ローンの借り手)がローンを返済できる見通しが立たなくなった場合、債権者がこの担保権を使って、裁判所での手続きを経て担保不動産を差し押さえます。
その後、強制的に売却する「競売」を通じて、債権者は担保不動産の売却代金から残債(未払いのローン残高)の回収を図ります。このように、不動産担保ローンを利用する際には不動産を失うリスクがある点に留意しましょう。
他に不動産担保ローンの債務者が返済不能となった場合の対応方法として、「任意売却」があります。任意売却は債権者が強制的に進める競売とは違い、債務者が一般市場で担保不動産を売却し、その売却代金で残債を返済するものです。
競売における不動産売却価格は、通常、一般市場での売却金額よりも低くなる傾向があります。そのため、競売で不動産を売却できたとしても、売却代金だけではローンを返済しきれない可能性があります。
一方で、任意売却は一般的な不動産市場で取引するため、競売よりも高い金額での売却が見込めます。ただし、担保の価値がローン残高を下回ってしまう「担保割れ」の状態だと、売却代金がローンの残高を下回ってしまうこともあり得ます。
いずれにしろ、担保の不動産を売却してもなお残債がある場合は、債務者は返済を続けなければなりません。返済の条件を見直すなど、債権者の協力を得ながら返済を継続する必要があります。
どうしても返済の目途が立たない場合、債務者は自己破産せざるを得ないケースがあり得ます。自己破産に陥る事態を防ぐためにも、借入れ前にしっかりとした返済計画を立て、やむを得ない事情により計画どおりの返済が難しくなった場合は、早めに債権者に相談することも大切です。
不動産担保ローンをご利用の際に、競売を回避するポイントはこちらの記事で詳しく解説しています。安心して不動産担保ローンを利用するためにも、あわせてご覧ください。
不動産競売とは?不動産担保ローンの利用で競売を避けるポイント
融資実行までに一定期間を要する
お金を借りたい方が正式にローンの申込みをしてから審査が始まり、さまざまな審査基準に照らして問題ないと判断されれば、ローン契約手続がおこなわれたうえで、借り手にローンのお金が交付されます。この一連の期間は、無担保ローンよりも不動産担保ローンのほうが長くなります。
不動産担保ローンでは、借り手となる方の返済能力だけでなく、担保となる不動産の担保評価を決めるための鑑定など、審査基準が多岐にわたるため、一朝一夕にはいかないとされています。
具体的な審査の期間は借り手や不動産の状態、また金融機関によっても異なります。いずれにしろ一定期間かかることを見越して、時間に余裕をもって申込みをおこなうと良いでしょう。
価値が低い不動産は担保にできない可能性がある
担保は債権者が貸し倒れのリスクに備えるためのものですから、価値がある不動産である必要があります。担保不動産の価値が低い場合、金融機関から担保として認められず不動産担保ローンを利用できない可能性があります。
流通性が低い、利便性が著しく悪いなどの理由で資産価値の低い不動産は、担保評価額も低くなります。場合によっては担保として認められない可能性もあり、仮に担保にできたとしても借りられる金額が少なくなるケースも考えられるでしょう。
例えば、再建築不可な物件や災害リスクの高い立地にある物件、老朽化した建物などは価値が低いと判断される可能性があります。また、借入時に担保とした不動産の価値が著しく下がった場合、「追加担保」を請求されることもあります。
不動産担保ローンを申込む前に、国税庁のホームページで公表されている「路線価」などを利用して不動産の価値を調べておきましょう。また、担保不動産の近隣にある類似した不動産の価値がいくらで売り出されているかを調べて、市場価値を把握することも大切です。
なお、不動産担保ローンの担保評価額の計算方法について、こちらの記事で詳しく解説しています。あわせて参考にしてみてください。
不動産担保ローンの担保評価額とは?算出方法や融資可能な不動産の例
諸費用がかかる
不動産を担保にするからこそ、発生する費用があります。不動産担保ローンの契約時、借り手が負担する費用の主なものは、次のとおりです。
| 説明 | 金額の目安(一般的な範囲など) | |
|---|---|---|
| 事務手数料 | 借り手から貸し手に支払う手数料 | 定額の場合と借入金の数%となる場合がある |
| 登記費用 | 担保不動産に抵当権を設定する際の法的手続きの費用 | 司法書士報酬+登録免許税(借入金額の0.4%が基本) |
| 印紙税 | 金銭消費貸借契約に貼付する印紙代 | 借入金額による(1,000万円超~5,000万円以下の場合は2万円、など) |
| 火災保険料 | 保険会社に支払う担保不動産の火災保険の料金 | 建物の構造・所在地・築年数・補償内容などによる |
事務手数料
事務手数料は、貸し手となる金融機関に支払う手数料です。いつ、どのように支払うかなど、タイミングと方法は金融機関により異なりますが、融資を実行するときに、貸し手が事務手数料を差し引いて借り手の銀行口座に送金することも多いようです。この場合、借り手が事務手数料の支払い手続きを別途おこなう必要はないことになります。
事務手数料の計算方法もさまざまです。固定の金額が設定されていることもあれば、借入金額に対して●%のような割合で計算されることもあります。割合の場合は1-3%が多いようです。どのように計算されて、具体的にはいくらなのか、契約前にしっかりと確認しましょう。
登記費用
不動産担保ローンが実行されるとき、担保となる不動産に「根抵当権」や「抵当権」などの担保権が設定されることは前述のとおりですが、その設定のためにかかる費用です。(根)抵当権設定の登記をする際にかかる登録免許税と、設定登記を担当する司法書士に支払う報酬をまとめて「登記費用」とされていることが多いです。
抵当権設定にかかる登録免許税は、債権金額(借入金額)の0.4%です。(根抵当権の場合、債権金額の部分が極度額となります。)
抵当権設定は専門的な手続きとなるため、司法書士に依頼するのが一般的です。貸し手となる金融機関指定の司法書士がいる場合もあります。抵当権設定にかかる司法書士報酬の相場は5-10万円などとも言われますが、交通費や通信費、その他の実費がかかることもありますし、ケースバイケースです。いずれにしろ、司法書士報酬の見積りは事前に発行されるはずです。内訳をしっかりと確認し、不明点があれば確認してから契約を進めるようにしましょう。
印紙税
不動産担保ローンにおいて借り手と貸し手の間で締結される契約書のことを「金銭消費貸借契約書」といいます。こちらの契約書は課税文書となるため、収入印紙を貼付することにより印紙税を納税する必要があるのです。印紙税の金額は、不動産担保ローンの契約金額に応じて決まります。
火災保険料
災害などで担保となる建物が破損した時に保険金がおりるよう、火災保険に加入しておく必要があります。前述の金銭消費貸借契約や関連する契約のなかで、建物の火災保険加入が借入れの条件とされていることもあります。金融機関によっては火災保険に質権を設定するなどの条件があるようなので、これについても契約前によく確認しておきましょう。
不動産担保ローンの活用例
ここまで不動産担保ローンのメリットとデメリットをご説明してきましたが、いかがでしたか?最後に参考として、不動産担保ローンの主な活用例をご紹介します。
開業資金として
新規事業の場合、実績がないためどうしても収益の見通しが不透明となりがちです。そのため、一般的な銀行のビジネスローンなどの審査に通らないこともあるようです。
これに対し不動産担保ローンの場合は、審査時に借り手の返済能力、不動産の担保評価、事業の将来性までを総合的に判断するため、独立・開業資金でも借りやすい側面があります。
独立・開業されるご本人が不動産をお持ちでなくても、ご親族所有の不動産を担保にして不動産担保ローンを利用できる場合もあります。
運転資金、納税資金として
独立・開業資金のみならず、事業所の移転や社会保険料・厚生年金保険料の納付など、事業においてまとまった資金が必要な場面で、広く不動産担保ローンが利用されています。一時的にお金を借入れてキャッシュフローを改善、資金繰りの厳しい時期を乗り越えてから借入金を返済するスキームをとっている企業は少なくありません。開業資金として利用する場合もそうですが、不動産担保ローンの契約時、事務手数料をはじめとした諸費用が発生する点は注意しましょう。
なお、運転資金の目安などは以下の記事で詳しくご説明しています。
おまとめローンとして
おまとめローンとは、すでに複数のローンを組んでいる方が、それらをまとめて返済するために新たなローンを借りて、一本化することです。
複数のローンを契約していると、それぞれ金利が異なったり、月に何度も返済日があったりと、管理が煩雑です。比較的大きな金額が借りやすい不動産担保ローンを活用して複数のローンをひとつにすることで返済日もまとまりますし、金利が下がって返済総額を抑えられる可能性もあります。
相続にかかる費用の支払いとして
お亡くなりになった家族の遺産相続が発生したとき、相続財産の中に一定価値以上の不動産があると、納税などのために多額の資金が必要になることがあります。相続税以外にも、代償分割をする場合にはその代償金、遺留分減殺請求を受けた場合の現金支払いなどが発生することもあるためです。相続財産である不動産を担保として不動産担保ローンを活用し、こういった相続時に必要な現金の問題を解決されているケースもあるようです。
リフォーム資金として
リフォーム資金の準備のために不動産担保ローンが活用されている例もあります。
少額のリフォーム費用であれば無担保で借りられるローン商品もあるようですが、大規模修繕などのために多額の費用がかかる場合、お金をどのように準備したらいいのか悩まれる方もいることでしょう。そんなときは、お手持ちの不動産を担保にどれくらいのお金を借りることができるのか、不動産担保ローンを取り扱っている金融機関に相談してみてはいかがでしょうか。
不動産担保ローンを利用する流れ
不動産担保ローンを利用する際の一般的な流れは、以下のとおりです。
詳しい順序は金融機関によって異なります。個別のケースがどのような流れになるのかは、各金融機関に確認したうえで、お申込みをされると良いでしょう。
Step1.相談
まずは、担保とする不動産の情報や、お借入れの目的を相談してみましょう。各金融機関のホームページでフリーダイヤル番号が案内されていたり、「ネット申込み」などのボタンが設けられていたりすることが多く、無料で相談できます。
相談したからといって、必ず申込みをしなければならないわけではありません。不明なことや不安があれば担当者に確認しながら、正式な申込みに進むかを検討しましょう。
Step2. 申込み
正式な申込みの段階で本人確認書類(運転免許証など顔写真付の身分証明書)の提示を求められるのが一般的です。申込書類に捺印するための印鑑(認印)や、過去数年分の収入確認書類も準備しておいたほうが良いでしょう。収入確認書類は、個人の場合は確定申告書や源泉徴収票、法人の場合は決算書です。
申込み時の必要書類やその他手続きについては、よろしければ以下の記事もご覧ください。
Step3.審査
正式な申込みおよび必要な審査書類が提出されると、本審査に入ります。借り手となる個人または法人および担保の不動産、両方についての審査です。住民票や納税証明書といった市区役所で取得しなければならない証明書類や、事業計画書の提出が求められます。何をいつまでにやるべきか、金融機関の担当者とよく確認して準備を進めましょう。なお、審査の結果、残念ながら希望の借入れができないこともあります。
審査の要点などはこちらの記事で詳しく解説しています。ご参考になさってください。
不動産担保ローンの審査とは?要点を押さえて無理のない返済計画を
Step4.契約
審査の結果、融資を実行しても問題がないと金融機関が判断すれば正式に契約します。ローンの契約日や契約時の持ち物(実印、印鑑証明書、その他証明書類など)を案内されたら、もれなく準備を進めましょう。
審査が通っても、証明書類に不足があれば契約が滞ってしまいます。最後まで気を抜かず、指定された書類や持ち物を用意しましょう。無事に契約を締結したら、融資が実行され金融機関から入金されます。
相談から契約までの流れについて、スムーズに進めるためのポイントをまとめておきます。
- Point1. お金を借りたい目的を明確にして相談する
- Point2. 現実的で無理のない返済計画を立てる
- Point3. 必要書類は期日に余裕をもって準備する
- Point4. 金融機関からの質問・説明には誠実に応答し、不明点は都度質問して解決する
- Point5. 申込みや契約の書類はしっかり読み、内容を理解したうえで、記入・捺印する
新生インベストメント&ファイナンスの不動産担保ローンへ申し込む際の流れは、こちらをご覧ください。電話かインターネットから無料で相談できるので、お気軽にご利用ください。
不動産担保ローンを利用する際の必要書類
不動産担保ローンを利用する際の必要書類は、以下のようなものがあります。 法人と個人(個人事業主含む)によって異なるものもあるため、確認しておきましょう。
法人の場合は以下のとおりです。
- ・商業登記謄本(登記事項証明書)または履歴事項全部証明書
- ・印鑑証明書
- ・決算書(2~3期分)、法人税申告書
- ・納税証明書(法人事業税・法人税など)
- ・借入計画書
- ・不動産登記簿謄本、公図、地積測量図、建物図面
- ・登記済権利証(または登記識別情報)
個人・個人事業主の場合は以下のとおりです。
- ・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- ・印鑑証明書
- ・住民票
- ・収入証明書(確定申告書(2~3期分)・源泉徴収票など)
- ・納税証明書(所得税・住民税・固定資産税など)
- ・不動産登記簿謄本、公図、地積測量図、建物図面
- ・登記済権利証(または登記識別情報)
必要となる書類は、借入れる金融機関によって異なる可能性があるため、確認しておきましょう。また、必要書類の中には手元に用意できるまでに時間がかかるケースもあるため、早い段階で必要書類を把握しておくと良いでしょう。
必要書類については、こちらの記事でも解説していますので、合わせてご覧ください。
不動産担保ローンの「正しい姿」を理解して「正しい使い方」を心がけよう
不動産担保ローンは、保有している不動産を担保として提供する点が特徴です。無担保のローン商品に比べて、高額な借入れに対応しているメリットがあります。
高い価値を持つ不動産を担保として供すれば、1億円程度の借入れも可能です。高額なお金を用意する必要性がある方にとって、不動産担保ローンは有用な手段の一つといえるでしょう。
ほかにも、無担保ローンよりも低い金利が適用される可能性が高く、長期間の借入れができるなどのメリットもあります。ご紹介した活用例のように、さまざまな場面で利用できるため、利便性も高いといえるでしょう。
一方で、返済不能となった場合は担保の不動産を失ってしまうリスクがあります。不動産担保ローンのご利用を検討されるときには、近い将来における事業の収益性や、無理のない返済計画を立てられるかを確認しましょう。
新生インベストメント&ファイナンスでは、最大10億円の融資に対応しています。 最長35年の返済期間を設定できるため、月々の返済額を抑えてご利用いただけます。
不動産担保ローンに関するよくある質問
最後に、不動産担保ローンに関するよくある質問を解説します。
申し込む際の参考になさってください。
Q:赤字決算ですが申し込みできますか?
経営改善に向けた取組み、事業計画などからご返済能力を多角的に審査します。
ぜひご相談ください。
Q:本人以外が所有する不動産を担保にできますか。
法人は、代表者など役員の方がご所有の不動産を担保にすることは可能です。
個人は、ご本人の配偶者やご両親など親族の方がご所有の不動産を担保にすることは可能です。
Q:金融機関や貸金業者からの借入金の返済資金を借入れることは可能でしょうか?
もちろん可能です。
ご融資期間を長くすることで毎月の返済額を軽減できるため、多くのお客さまにご利用いただいております。ただし総量規制によりご希望に添えないこともあります 。
総量規定については下記の記事でも解説しています。